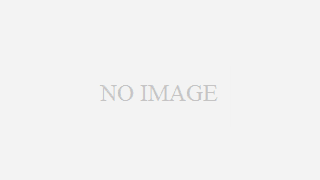 ウチナーグチ入門
ウチナーグチ入門 第2回 – ことわざ「いじぬ んじらー てぃーひき、てぃーぬ んじらー いじひき」
沖縄のことわざ いじぬ んじらー てぃーひき、てぃーぬ んじらー いじひき ▼意地ぬ 出じらー 手引き、手ぬ 出じらー 意地引き 意味・・・怒りを覚えたら手を引っ込め、手が出そうになったら怒りをしずめなさい。 『ウチナーグチ入門』(沖縄文化...
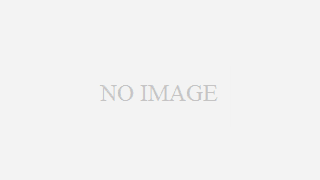 ウチナーグチ入門
ウチナーグチ入門 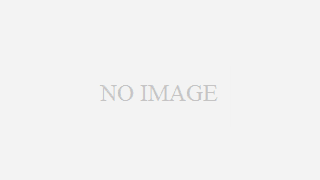 泡盛学講座
泡盛学講座 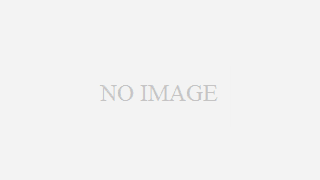 ウチナーグチ入門
ウチナーグチ入門 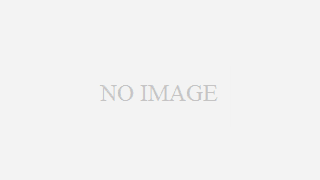 泡盛学講座
泡盛学講座 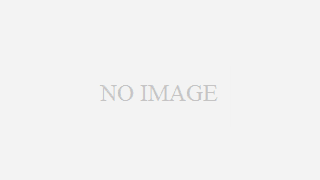 泡盛学講座
泡盛学講座 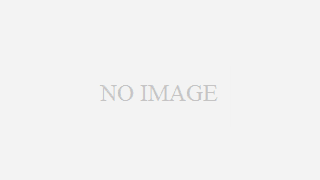 泡盛学講座
泡盛学講座